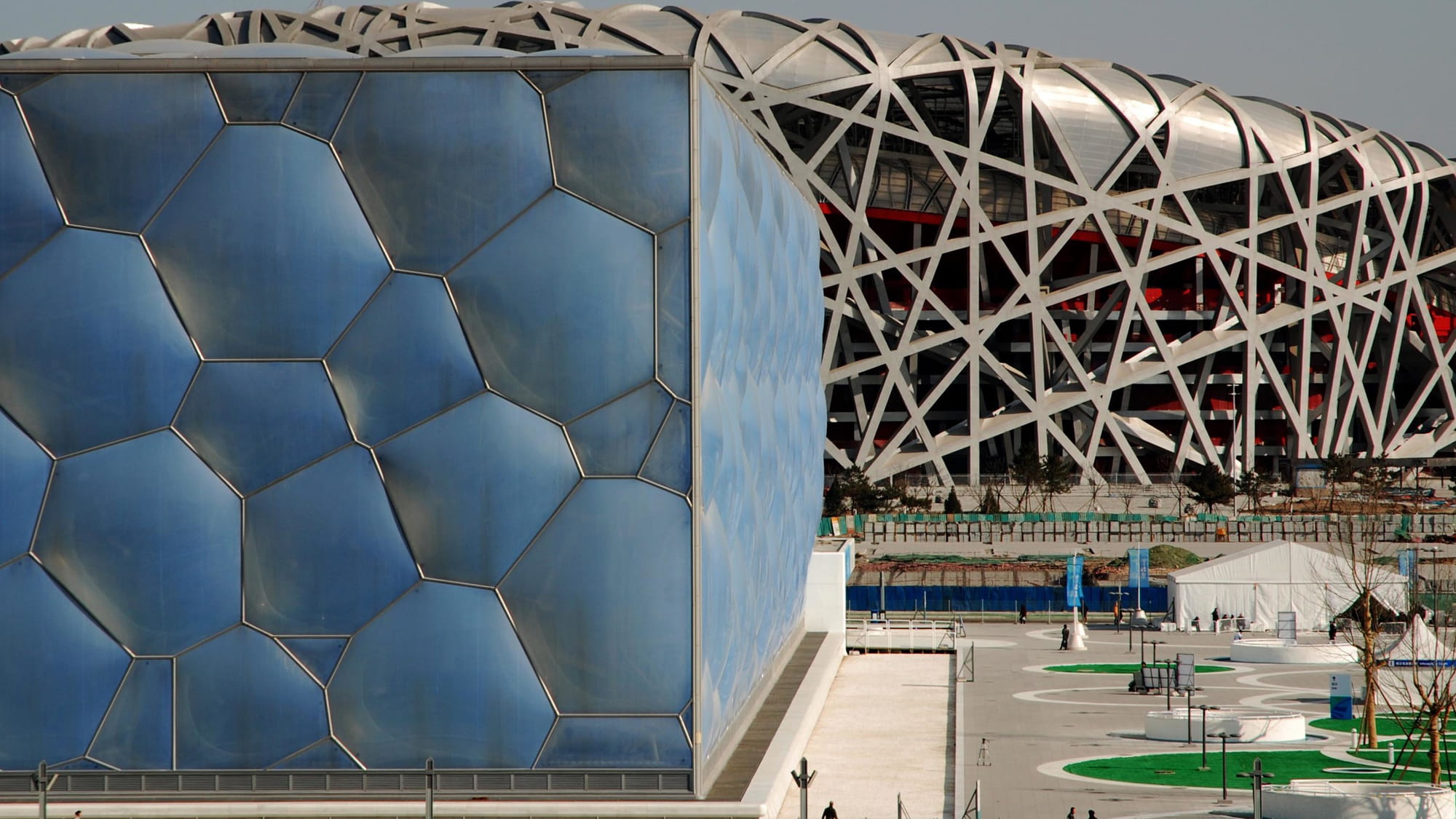瀬戸內海の小さな島、犬島にある銅の製錬所は1909年に建設され、明治の終わりから大正中期にかけ日本の近代化を擔いましたが、銅の暴落や経済的価値の変化により、わずか10年ばかりで閉鎖されました。近代化産業遺産に登録されているこの跡地を「犬島アートプロジェクト」の一環として保存?再生することにより、犬島精錬所美術館が生まれました。
環境×アートで、島を再活性化
既存資源を生かし、そこから生まれるアートや建築を通して、地域経済を再活性化することを目的として福武總一郎氏により構想されたプロジェクトにおいて、島に殘された煙突や工場跡を軸に建築家?三分一博志氏によって美術館が設計されました。銅の精製錬の副産物であるスラグやカラミ煉瓦、犬島石などの既存資源を生かし、來館者が太陽光や地熱、風などの自然エネルギーを體感するだけでなく、訪れることで自然にも貢獻できるような循環する建築を実現するため、アラップは構造設計と建築環境コンサルティングを擔當しました。
環境シミュレーションの技術を生かした、
ゼロ?エネルギーシステム
建築家?三分一博志氏のビジョンを具現化するため、アラップは、プロジェクトの初期段階から検討に參加し、環境解析を行っています。
完成した施設の室內環境は、晝夜、四季を通して、地形や構造物に內在する再生利用可能なエネルギーを総合的に取り入れ、循環させています。機械設備は一切使用せず、自然エネルギーによってパッシブに建物內の環境をコントロールしています。
地中埋設された回廊スペースは、鉄壁を採用し、壁にウェーブをつけ、回廊狀の空間とすることで夏季には暑い外気とより低溫の地中との間で熱交換を促し外気を冷卻する役割を果たしています。また、この直角に折れ曲がる回廊狀の展示スペースに配置された鏡は、通路を直線に見せる仕掛けとしてだけでなく、美術館の奧まで自然光を導きます。そして、建物の特徴である煙突の高低差と太陽熱を活かすことによって自然換気を促します。
銅製錬所の既存資材を、そのままに
島に殘されていた1萬7,000個のカラミ煉瓦資材はデザインとしてだけでなく、熱伝導性能や熱特性を活かして建物內の壁や床に利用されています。地中熱を利用した冷卻の通路や、太陽エネルギーを蓄え保熱効果を擔うホールは、年間を通して安定した室內環境を生みだしています。既存資材がそれぞれに持つ特性に、太陽光、地中熱、気象條件などの自然エネルギーを組み合わせることで、殘された構造物を再生し、快適な空間の実現を可能としました。
サステイナビリティの実現
アラップは、高度な環境解析の技術を用い、建築環境を成す要素について総合的に検討を行いました。竣工後に継続して行われている現地実測のデータにおいても、その検討の実効性が確認されています。環境に負荷を與えず、かつ快適な建築環境を実現した循環型建築です。
受賞歴
2010年度 日本建築大賞
2011年度 日本建築學會賞 / 作品
第53回 建築業協會賞(BCS賞)
 ;
;